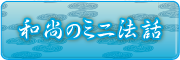和尚のミニ法話
新盆施食会のおとき
8月4日は新盆施食会(あらぼんせじきえ)でした。新盆は所によっては「にいぼん」とも言うらしいですが、当地では「あらぼん」です。
連日の猛暑の中、当日もとても暑くお参りの方々は黒の礼服ですので汗だくでした。
法要のあとのおときが写真です。
メニューは、
平(ひら):こんにゃく、油揚、なす、南瓜、椎茸、ユウゴウ(夕顔)、人参、車麩、オクラ
木皿(きざら):ワラビのショウガ和え(わらび、人参、エノキ、キュウリ)、温室みかん
坪(つぼ):なすのクルミ胡麻和え、ブラックベリー
ごはん:地元産コシヒカリ
汁:豆腐の味噌汁
香の物:水ナスの漬物(氷で冷やして)
いかがですか。ごちそうでしょ。おいしそうでしょ。光照寺のお勝手さん方が朝から汗ふきふき調理しての大御馳走です。
光照寺のおときは、どこに出しても恥ずかしくないどころか自慢したいくらいです。ところが最近食べてくださる参詣者が少なくなってきて残念です。
次回のおときはは秋の彼岸会です。お参りに来ていただければ、おいしいおときが待っています。(お代は不要。お賽銭で結構です。)
「お盆は仏壇に桃」は定番でなくなってきた。
三条市大島の果樹農家の檀家さんから桃をいただくようになりました。初物は6月の末頃でした。今年は大きくないが甘いとのこと。
私の感覚では、「桃の時期=お盆」という図式なので、桃を頂戴すると夏が来たなあと思うのです。昔は、大抵の家のお盆の精霊棚には果物が供えてありそのほとんどが桃だったと思います。そして熟しすぎて腐る一歩手前のような甘ったるい匂いが漂っているのです。私にとって桃のイメージはお盆の棚経(僧侶にとっては苦行の一つかと)と直結するのです。
ところが、桃農家さんの話では、桃の出荷は以前よりも早まっていてお盆にはほとんど終わってしまうとのこと。代わって梨やぶどうがが出回ってくるのだそうです。今日のTVニュースで、早くも南区白根でぶどうの収穫が始まったと伝えていました。
今年の棚経では桃でなく梨やぶどうのにおいを嗅ぐことになるのでしょうか。
草取りボランティア作業 ぎりぎりセーフ男の本領発揮
昨日28日、早朝6時より盆前の草取りボランティア作業を行いました。20人程の参加でした。朝早くからありがとうございました。男性陣は裏庭の池の周辺を、女性陣は永代供養墓の周りと大門の両側で作業をしていただきました。やはり大勢の力は大したものできれいになりました。
昨夜からの大雨(台風の影響?)で中止も考えましたが、雨も上がりましたので予定通り実施しました。解散した後にザーと降ってきて、作業の時だけ止んでくれました。私は昔から雨男でしたが「ぎりぎりのところで何とかセーフ男」でもあります。思い返せば、平成18年の晋山結制の大行事の時もそうでした。朝から雨でしたが稚児行列の時だけ止み、法要中は降り、写真撮影では止みました。決して晴れはしないのだけれど予定は何とかこなせる・・・というように。今回もギリギリセーフ男の本領発揮というところでした。(仏天のご加護かも知れませんね。)
作業後に振舞ったこんにゃくの煮つけは好評でした。また次回も(こんにゃくを目当てに)おいでください。
振鈴当番はヒグラシ
梅雨が明けました。開けた途端猛暑です。二三日前からヒグラシが振鈴当番を任されたようで、決まって早朝4時15分になると、カナカナカナ・・・と鳴き始めます。一匹が鳴くとそれに呼応するように仲間も鳴き始めて山中大合唱です。山で鳴いているのはいいのですが、今朝は庫裏のすぐ近くにいたようで、大音量の振鈴でした。「ああ今日も始まったな。起きるとするか。」ということで一日がスタート。
夕方は17:30に鳴きますね。
光照寺山内では夏の虫が大集合で、今はシオカラトンボ、クロアゲハがたくさん飛んでいます。日中はアブラゼミ。ジージーという声を聞くと暑さが倍増する感じです。オニヤンマはもう少し後でしょうか。
あらら、今日アブがいました。お盆にかけてアブとの戦いが始まります。刺されないように要注意。
虫ばかりでなく珍しいものと遭遇しました。キツネです。5時頃、本堂から外を眺めていたら、六地蔵様のお堂の前で発見。いるんですね。初めて見ました。(光照寺は山寺ですが、クマやサルはいませんのでご安心を。)
写真は、アジサイの花摘みと剪定の様子。アジサイの時期も終わりです。来年のために花を切り落とします。花から二節くらいの葉の付け根に来年の花芽ができます。ふつうはこの辺で切りますが、姿かたちを考えてもっと強く切り落とすこともあります。強く剪定すると来年の花芽はできないかもしれません。(この作業は家内が担当しています)
仏像レディース来山
突然訪ねて来られた仏像好きの二人の女性。
「ご本尊はお釈迦様ですか」
「脇侍仏は普賢菩薩と文殊菩薩ですね。」・・・ほほー、よくご存じで。
「普賢、文殊の座像は珍しいですね。たいがい立像ですものね。」・・・さまざま見ておられるのだな。
地蔵堂に案内して、お厨子の前の地蔵仏を「お前立」ですと説明すると
「(本尊地蔵仏は)秘仏ですか。」・・・おぬし、なかなかやるな。秘仏などと言う言葉を知っているとは!
一通り巡堂され、丁寧にお礼を述べられてお帰りでした。(供物料を頂戴しました。ありがとうございました。)
「仏像ガール」という言葉を以前耳にしたことがありますが、ガールでなくてレディーでしたが実際におられるんですね。
このお二人は、近くの温泉に行く途中にHPで調べて立ち寄ったとのこと。いい趣味をお持ちですね。
今朝のアジサイは「コサージュ」です。青色ですが咲き始めは白に黄色がかった色をしていてとても奇麗です。