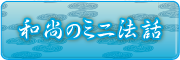和尚のミニ法話
布施というは貪らざるなり②
布施というは貪らざるなり。「独り占めしない」ということでもあります。
本山では食事の時に「生飯之偈(さばのげ)」を唱えます。
汝等鬼神衆(じてんきじんしゅう)
我今施汝供(ごきんすじきゅう)
此食偏十方(すじへんじほう)
一切鬼神供(いしきじんきゅう)
修行中はよく意味も分からず、ただ唱えているだけでしたが、大事な偈文だったのです。
「独占しない」ということについて、新潟日報の日報抄(2011.7.8付)を紹介させていただきます。
『仏教の作法の一つに「生飯(さば)」がある。食事の際に、ご飯の一部を取り置き、鳥獣などに施すのだという。食べ物を独り占めにせず、すべてのものに分け与える。そんな考え方が根本にあると聞いた▼先日テレビで曹洞宗の僧侶の食事風景を見た。1人当たり7粒のご飯が器に集められ、境内に寄ってくる小鳥に供されていた▼まねたわけではないのだが、拙宅の庭を遊び場にするスズメたちに数日前からコメを分け始めた。・・・(中略)・・・カーテンのすき間から観察して分かったことがある。彼らもまたわずかな糧を独り占めしない。一羽が数粒ついばむと、入れ替わりに別の一羽が舞い降りる。植木の枝には見張り役らしい一羽がとまる。誰に教えられたわけでもない。野性を生き抜く知恵だ▼3月11日夕から翌朝にかけて、津波から逃れた建物で、子供たちがポテトチップスなどを分け合って空腹をなだめたという記事が忘れられない。暗闇で小さなかけらをやり取りする光景を想像するだけで涙がでる。▼日本の食文化を世界無形文化遺産に登録する準備がはじまった。・・・(中略)・・・世界が注目するのは健康的で美しいところだという。しかし、私たちの食文化には、それ以上の価値があることが大震災で確かめられた。「独占しない」それは既に立派な無形の財産である。』
私はよく法事等の折に、祭壇に供えられた霊供膳の生飯(さば)を示して、この話しをさせてもらっています。「自分のものを分けてあげる」できそうでなかなかできないものです。ですが、さりげなくスッとできる人になりたいなと思います。
写真は、本堂壁の獅子の絵です。(本文とは関係ありません)
布施というは貪らざるなり①
「衆生を利益すというは四枚の般若あり、一つには布施、二つには愛語、三つには利行、四つには同事、・・・」(修証義第四章) この四つを「四摂法(ししょうぼう)」と言い、道元禅師はこれを菩薩行としてとりわけ重視されました。
布施についてのお話しをします。「布施というは貪(むさぼ)らざるなり」。むさぼらないということ、つまり欲心のないことであります。あれもこれも、みんなおれのものとばかりにガツガツしないということです。あれも食べたい、これも食べたい、人のものを奪っても自分のものにしたい。そんなガッついた人になりなさんなということです。では、どうすればそうならずにすむのでしょう。それは、人に施すことです。自分のものを少し分けて他の人に差し上げることです。独り占めしないで分け与えなさいということです。人から物をもらっても、お礼を言わない人がいます。お中元でもお歳暮でも、夕食のおすそ分けでも、「どうも」とか「ありがとう」の一言だけですませる方がいます。あげた方は「おいしかった」とか「いい味付けですね」とか「子供が大喜びで」とか言ってもらえるとうれしいし、あげた甲斐があったというものです。お礼の苦手な人は、人に物をあげる喜びを知らない人なのかもしれません。布施することは自分にとっても喜びなのです。
月経に伺うたびに、野菜を持たせてくださる農家の檀家さんがおられます。私は恐縮至極なのですが、私が受け取るとき、その方はうれしそうな顔をされます。
お客様を手ぶらで返しては失礼だ、という儀礼から一歩進めたところに「喜び」があるのです。
写真は、「地蔵様の頭巾を縫う会」で参集された方々の奉納頭巾と前掛けです。寸法と縫い方について、トップページ左側の「お知らせ」にアップしてありますので、どうぞこしらえてみてください。
「地蔵様の頭巾を縫う会」ご参加ありがとうございました。
1月25日、初の試みでしたが「地蔵様の頭巾を縫う会」を開きました。檀家の奥様方を中心に12人の皆様からご参加いただきました。ご自身の願い事を胸に、一針一針真剣に縫っておられました。地蔵様はきっと皆さんの願いを叶えてくださることでしょう。初めて縫うという方が多かったようですが、講師のMさんの手ほどきで上手にこしらえてくださいました。Mさんと家内とであらかじめ型紙を作り、布を裁っておいたので、予定の3時間で何とか出来上がったようです。「頭巾を縫う」と口では簡単に言えますが、なかなか大変な作業なのですね。本当にありがとうございました。そして、ご苦労様でした。
彼岸前に地蔵様に被っていただこうと思います。彼岸参りにおいでの方をきれいなおべべの地蔵様が迎えてくださることでしょう。地蔵様は六道能化。衆生の苦しみを救い願いを叶えてくださいます。どうぞ信心をもってお手合わせください。
また、頃合いを見て第2回目を行いたいと思います。いつ頃がいいのか、どんなやり方がいいのか、いろいろご意見を伺って決めていこうと思っています。
仏前結婚式
昨年6月、当寺二女と智玄上座さんの仏前結婚式(檀家・近所披露)を本堂で行いました。仏前での結婚式にはなかなかお目にかかれないということで、多くの檀家さんから来山いただきました。「本堂で挙げるのもいいものですね。」という大方の評判でした。
ところで、新潟県曹洞宗青年会が周年事業として、仏前結婚式の普及に取り組んでいます。その名も「結の仏(ゆいのほとけ)」。新潟のご当地アイドルnegiccoがポスターのモデルをつとめてくれています。3人ともかわいいですよね。光照寺も、この青年会の取組に賛同しています。お知り合いに仏前で結婚式を挙げたい方がおられましたら、どうぞご検討ください。今なら先着5組まで、式師代や会場費用等を青年会でもってくれますし、衣装代のうち上限10万円の補助もあるようですよ。これから式を挙げようとされる方、事情があって式を挙げれなかった方、新潟県曹洞宗青年会のHP http://niigata-sousei.jp/ をご覧ください。
「光照寺の本堂で式を挙げたい」OKですよ。「式師もお願いしたい」OKですよ。
1月25日(日)「地蔵様の頭巾を縫う会」です。参加者受付中です。お電話ください。
僧侶の法階 ~位(くらい)の呼び方~
「婿さんを坊さんとしてどう呼べばいいのでしょうか。」 檀家の方からよく聞かれます。
「『若方丈さん』でいいですか。」
「それはだめですね。」と私。
「じゃあ、『若和尚』ならばどうでしょう。」
「それもだめですね。うーん、年齢がまだ幼なければ小僧さんということになるのでしょうが、いい大人ですのでね、『若さん』か『上座さん』でしょうね。」とお答えしています。
写真のように(見づらくてすみません。写真をクリックするとよく見えます。)、宗門では修行の段階に応じた呼び名「法階」があります。得度をして僧侶の仲間入りをすると「上座」に、立身し首座(しゅそ)という職について法戦式(ほっせん式)を行うと「座元(ざげん)」に、永平寺・總持寺の両大本山にのぼり、一夜住職として朝課の導師を勤める瑞世(ずいせ)を終えると「和尚」になり、結制安居の修行を経て「大和尚」となります。私は大和尚ですが、若さんはまだ得度をしただけですので、上座なのです。今後、修行を積み重ねていきますので、応援してやってください。
写真は、宗務庁刊行の「寺院のための手引書」の一部を撮影転載しました。
お知らせ:「地蔵様の頭巾を縫う会」を1月25日に開きます。どなたでも参加できます。お誘いあわせておいでください。(トップページ左のお知らせをご覧ください。)